「どう死ぬと幸せか」
誰もが一度は漠然と考えることである。
人間はいつか死ぬ。
生きていれば、近しい人の最期にも立ち会う。
多くの臨終に立ち会ってきた医療者は別の問いを持つかもしれない。
「どう死ぬと不幸が少ないか」
駆け出しと老練
内科を志す若者、専攻医は高齢者の治療に積極的に関わる。
誤嚥性肺炎も専門とするところだ。
担当に付くと、早速、抗菌薬を投与し、嚥下機能が低下した患者に対して、食事を止めて、経管栄養を行う。
栄養が無ければ生きられませんから、と事実を述べる。
一日に必要なカロリーを計算し、感染症のため係数を掛けてかさ増しする。
一方、鼻に入った管は不快感が強く、患者は頻繁に引っ張ろうとする。
我々は患者の治療のため手足を抑制する。
ここは安心安全を理念に掲げる病院。
危険のないよう医療を受けていただく。
しかし認知症の進んだ彼らには、どうしてこんな状況になってしまったか分からない。
見慣れない天井の染みを見つめながら、家族はどこに行ったのか、家に帰って子供にご飯を作ってあげなくては、とやるべき事を思い出す。
すると、外せないはずの抑制器具から逃れられる。
彼らは縄抜け名人ではない。
昼間も夜中も貫き通した執念の成果である。
成し遂げた患者を見つけて、医療者は落胆する。
(あぁ、また入れ直さなくては…)
過去の勤務地では内科当直の際に、朝の5時は鬼門だった。
朝食に間に合うように胃管を再挿入せねばならない。
夜が明ければ通常業務が始まるので、留置から確認のレントゲン撮影までのわずかな時間も惜しく仮眠を取る。
そして次の成功者の連絡を受け、再び起こされる…
魔法の言葉
いかなる治療を施しても、死の瞬間は訪れる。
今や自宅ではなく病院で亡くなることが当たり前の時代。
医者も家族も病院で最期を迎えることに納得できないが、それを希望する。
生命維持と安全を提供する病院では、物語の終わりを「DNAR」という魔法の言葉で締めくくる。
多くの場合、挿管×、胸骨圧迫×、昇圧剤×という飾りを添えて。
実施の有無で揉めないよう、皆で念入りに確認する。
冴えない専攻医は、ベテラン看護師に叱責される。
「先生!胃管○なんですか!×なんですか!カルテに残して下さい!!」
細かな記述を加えると、丁寧な姿勢として捉えられる。
強心剤×、輸血×、透析×、経管栄養×、静脈栄養×…
現場からの評判も良い。
×が書いてあって分かりやすい、と。
曖昧さが生むもの
終末期の路線を決める上で、アラカルトで問う意志決定は最適なのだろうか。
ある若い内科医が患者家族と相談して、このような方針を打ち立てた。
挿管×、胸骨圧迫○
いったい何がしたいの、私には分からなかった。
命を助けたいなら胸骨圧迫と同時に挿管して人工呼吸器にも接続すべきである。
酸素は与えないが、心臓は力強く押さえつけて動かす。
果たして治療と呼べるのだろうか。
すぐに矛盾を指摘したが、薄々感じていたことが浮かび上がる。
個別に問うことが全てなのか?
救急学会では、このような○×形式のDNAR指示を、partial DNARとして苦言を呈している。
救いたいなら全部やる、そこで最期と判断するなら半端なことはしない。
厳密には終末期の治療計画とDNAR指示を混同するのも誤用である。
DNARは心停止時に有効な指示であり、治療を差し控える理由にはならない。
しかし現場では、DNARは何もしないという意識は根深い。
「先生!DNARなのに輸血するんですか?」
…
とはいえ、これも仕方が無い。
終末期とは何とも儚く脆い言葉である。
心停止する少し前の状態を定義する分かりやすい基準はない。
人がいつ亡くなるのか。
誰も正確に予想できないことにも起因する。
私はDNAR指示を厳密な定義で運用する人にも異議を申し立てたい。
心停止する数分前、心拍数が落ちて1分間に10回や20回となった時、患者や家族にペースメーカの話をしているか?
体外式ペースメーカ×とも書いてない。
それなのに誰も慌てない。
心拍数が落ちて循環不全を起こしたらペースメーカの適応を考慮と、救急の教科書には書いてあるのに。
もちろん今際の際に体外から電流を加えることを、私は是とは思わない。
結局それぞれの立場で都合の良いように解釈している。
言葉遊びをしたところで、誰も納得しない。
インフォームド・コンセント
○×の確認のみを目的とすると別の問題も孕む。
こんな場面を想像して欲しい。
当直明けの朝、ふらりと立ち寄った喫茶店。
コーヒーを頼もうとすると、こう問われる。
「豆の産地は?挽き方は?」
「お好みでどうぞ。自由に選んでいただいて構いません」
ありがたい提案のようで、率直に言えば、困る。
私はコーヒーの専門家ではない。
正直、メニューの一番上にあるブレンドで構わない。
医療ではどうか。
「挿管は?心マは?昇圧剤は?栄養は?透析は?」
切迫した状況なので早く決めてください。
急に呼びつけられて混乱している家族に、次々と専門用語を投げ付ける。
訳の分からないまま○×をつけ、同意書にサインする。
選ばせるようでいて、責任を移し替える。
これをインフォームド・コンセントと言う。
少し意地悪な書き方をしたが、あながち間違っていないと思う。
意志決定の方法
パターナリズム、インフォームド・コンセント、シェアード・ディシジョン・メイキング、アドバンスド・ケア・プランニング。
横文字の並びに目眩がする。
小難しい用語の解説は成書に任せるが、何となく、どれもしっくり来なかった。
その理由も分からなかったが。
喫茶店のマスターはお勧めを提供しても批判はされない。
コーヒーと治療は同列に語れないので、医師が選択肢なく一つの治療法のみを提案すると、パターナリズムという古い考えだと揶揄される。
では均等に情報提示するのか?
こっちは成功率○%で死亡率△%、あっちは◇%で…
口で話されても分からないし、最期に至るまでの治療過程はまるで想像が付かない。
素人の判断の根拠には到底なり得ない。
『納得』の意味を問う
内科ローテーションの頃、消化器内科の指導医は80代後半の寝たきりの患者に大腸カメラを勧めようとした。
体調不良で撮影したCT画像では、多発肝転移らしき像が映っており、その原発に大腸が疑われた。
治療方針を決める上で、診断の確定は有効である。
がん診療に組織診断は欠かせない。
しかし、老い先短い患者に行う意義はあるのか?
がんが見つかったとて、手術も化学療法も耐えられない。
様々な治療や検査を差し控えても良いと思える状況だ。
痛くなればモルヒネがある。
モルヒネに天井効果はないので、苦痛を和らげることは、医学には可能。
それで十分ではないのか。
検査をすれば、身体的負荷だけでなく、治らない病気を抱えている事実を突きつけられ精神的な苦しみも増えるだけではないか?
消化器内科の指導医は、決して自己満足で治療する先生では無かった。
内視鏡室に泊まり込み、誰よりも多くの患者を抱え、医業に自らの人生を捧げる覚悟を決めた人だった。
それだけに、なぜ大腸カメラを勧めるのか分からない。
病状説明に付き添うと、こんな言葉が出てきた。
がんと診断しても治療することは出来ないでしょう。
検査をする理由は皆さんが納得することです。
なぜ調子が悪くなったのか、原因不明のまま亡くなることに納得がいかなければ、大腸カメラを行う意義はあります。
『納得』とは何なのか。
専攻医を終えた頃
終末期の駆け引きを制する急所は、家族の合点にある。
極端な話、非業の死を遂げたとしても患者は訴訟しない。
物申すのは家族。
だからと言って患者に不利益を与えるわけではないが、我々の人生を守るため家族の理解は要点。
そう錯覚した。
終末期が如何に辛く苦しいものであるか説くことで、同意を引き出すこともあった。
実際、誤嚥性肺炎に経鼻胃管を入れて身体抑制することは、自分としても受け入れられなかった。
患者は幸せそうに見えなかった。
「口から食べられなくなったら最期です」
重い言葉との自覚はある。
それでも、事実を歪めて偽りの希望を見せることの方が、かえって残酷だと思う。
「全ての食事を止めて栄養のチューブを入れて、抜かないように体を縛るよりも、誤嚥や窒息を覚悟の上でも食べられそうな食事を摂って貰うのが幸せだと思います」
認知症が進行した人生の終末期では、経鼻胃管を入れても、胃瘻を作っても、食事を止めて点滴で栄養を入れても寿命は延びないと研究で示されている。
次第に誤嚥性肺炎に入れる経鼻胃管が減っていった。
医師としてエビデンスに基づいた治療を提案するのは当然のことでもある。
科学的根拠を元に語りかけた。
だが、それだけでは届かない何かがあると気づくのは、もう少し後の話である。
些細な準備、大きな成果
ある心不全の患者の話をしたい。
70代の男性で、かなり心臓の機能が悪い。
本来ならば心臓突然死の予防のために植え込み型除細動器が考慮される病状だ。
しかし機械を入れてまで長生きはしたくないという希望を尊重し、飲み薬のみで治療をした。
ある時、「けいれん」で搬送された。
病院到着時には頓挫しており、会話も可能だった。
診察した若い内科医は、抗けいれん薬を投与し、経過観察を目的に入院させた。
しかし入院して数時間後、定時巡回で亡くなった状態で発見された。
たまたま通りかかった私は、致死性不整脈による心臓突然死だと察知した。
目の前で心室細動を起こした人を診たことがある人は少ない。
すーっと意識がなくなる人も入れば、目を見開き、全身の筋肉に力が入って強ばり、ガクガクと震えるように四肢を曲げる人もいる。
これを「けいれん」と表現するのだろうが、本丸は脳ではなく心臓の可能性がある。
入院後には心電図モニターが付いておらず、詳細は分からない。
見逃しがあったかもしれない。
トラブルを予期し、家族には外来主治医だった私が話そうと提案し、気を引き締めた。
患者の妻は泣いていた。
口の中が乾いていく。
呼吸を整え、事実を正確に伝えようと、慎重に言葉を紡いだ。
返ってきたのは思いがけない返答だった。
「あなたが主治医の先生でしたか。
主人は先生から長く生きられないと言われたことを私にも話してくれました。
だから後悔のないように色々とやっていました。
ありがとうございました」
深く感謝をされた。
遡ること数ヶ月前に、患者とのやり取りを思い出した。
いつもと変わらない外来で、不意にこんなことを聞かれた。
「先生、私はあと5年、生きられるか」
この患者の心臓の機能や内服薬、機械の植え込みを拒否した経緯を踏まえて思慮深く、しかし心臓の専門家として誠実に返答した。
「5年は不可能でしょう。1-2年かもしれない」
少し間があって、
「そうか…」
と一言だけ漏らして、この日の診察は終わった。
1分にも満たないやり取りだった。
しかし、このわずかな時間が患者や家族の受容を生んだのだと信じたい。
自ら死の準備をする患者は少ない。
こちらから促しても、死は忌避される。
そもそも医師自身が終末期の話を回避したがるデータもある。
予後を口に出すことを皆が嫌がる。
医師は患者の期待を裏切ることをためらう。
この患者は運が良かった。
自ら死について考える質問をした。
そして私も幻想をいだかせないよう真摯に応えた。
少しだけ。
本当にわずかな時間、語り合うだけで良い。
深く心に響いた。
延命治療とは何なのか
終末期の話し合いでは、「延命治療をしないで下さい」と依頼されることもある。
延命治療という言葉は多くの人が理解しているつもりになっているが、ひどく曖昧な表現である。
人工呼吸器や胃瘻は分かりやすい形をしている。
では、誤嚥性肺炎に抗菌薬を投与するのはどうだろうか?
認知症の進んだ誤嚥性肺炎への抗菌薬投与は、生存期間を平均で200日ほど延長させるが、苦痛は増加するという研究結果がある。
点滴をつなげば患者は引っ張って抜きたくなるので抑制もセットになる。
自分の意志で水を飲むことも出来ない。
サラサラした水分は誤嚥のリスクが高くて与えられない。
嚥下に配慮し、色違いのドロドロばかり並べられる。
苦痛と寿命を天秤にかけられた状況を延命と呼ぶのなら、抗菌薬は延命ではないと言い切れるのか?
「人工呼吸器をつけて辛い思いをしながら長生きするくらいなら、苦痛の少ない治療を優先して欲しい」
そんな希望にもそぐわないかもしれない。
しかし多くの医師は抗菌薬を使う。
肺炎球菌や口腔内の嫌気性菌をカバーするためにベータラクタマーゼ阻害薬を配合した広域ペニシリンが有効だと医学的に考察する。
使用の是非など議題にならない。
…とは言え、私もまた投与を指示してしまう。
なぜならば肺炎で入院するのに抗菌薬を使わないのは、他の医師、看護師、患者、家族、多くの人から疑問を持たれる可能性がある。
こういった行動を、社会心理学者ソロモン・アッシュは『集団思考』と呼んだ。
間違っていることを知りながらも多数意見にくみする。
あるいは「ちゃんと治療しなかった」と糾弾される恐怖もある。
自己防衛的な医療は、Defensive Medicineとしても取り上げられる。
抗がん剤が効かなかった。
カテーテル治療をしたが、効果はなかった。
限界を示すことは、万人に仕方が無いという諦めを生む。
医師の40%は効果が無いかもしれないと思う治療をする。
患者の「良くなるかもしれない」という淡い期待を、自らの手で砕きたくないから…
循環器内科医のアイデンティティ
誤嚥性肺炎を診るために循環器内科医になったのではない。
昼も夜も病院に張り付くのは、命を救いたいという純粋な思いと、修練によって叶える技術があるとの自負がある。
カテーテル手術はその象徴とも言える。
上司はそれを“ご褒美”として語り、やり甲斐と引き換えに過酷な医療現場を支える。
日常の臨床からチャンスを見いだし、大義を携えて手術室へ向かう。
治療しなければ命は助からない。
しかし、かつての消化器内科の指導医の示した納得の形とは違う気がする。
もちろん手術に望む医師は真剣だ。
崇高な目的に疑念はない。
だが、人間の意志決定には無意識が大きく影響することも事実として受け入れなければならない。
心理学の実験では、被験者は同じ車を見たときに、横に美女が立っている方が性能が良いと判断する。
あるいは老人に関する言葉に沢山触れた後、若者であっても歩くスピードが老人のようにゆっくりとなる。
人の判断は、個人が考える以上に環境や些細な要素の影響を受ける。
であるならば――
「カテーテル手術をもっとやりたい!」
強い願望が、知らず知らずのうちに判断や行動に影響を与えている可能性は否定できないのではないだろうか。
治療をしないことで長生きする
終末期の患者の診療を、内科医と老年科医が担当した場合に、患者の経過にどのような違いが出るのか。
それを検証した研究がある。
結果は、大方の予想通りだった。
死亡率は同等だったが、老年科医の治療では身体機能が落ちにくく、うつ病の頻度も少なかったという。
カテーテル手術や内視鏡による処置をせず、抗がん剤も使わない。
過剰になりがちな薬を整理し、介護サービスを調整して孤独に配慮し、食事に気を遣う。
前のめりになるのでも、後退するわけでもない。
彼らの極意は、患者の全体を見渡し、調和を整えること。
結果も伴っている。
しかし現実には大きな課題が横たわっている。
それは――採算が合わない、ということ。
手術や集中治療は、収益の柱でもある。
加えて「治療をしなかった」と批判を受ける可能性もある。
もちろん磨き上げた手術の腕が生かされる場面もない。
それでも私は思う。
必要な医療は何なのか、考えていきたい。
印象的な患者がいた。
90代の女性、自宅で動けなくなって受診をされた。
病院嫌いで、健診も受けていなかった。
心雑音を聴取し、重症の大動脈弁狭窄症をみつけた。
BNPという心臓の負荷を示す数値は正常上限の50倍まで上昇していた。
胸水や浮腫はないため、循環が破綻しているわけでは無さそうだ。
専門医の判断としては利尿剤はむしろ使わない方が良い。
根本的な治療として、開胸手術は困難な年齢だが、カテーテル手術(TAVI)は出来るかもしれない。
患者は認知症で意志決定は困難だった。
家族は手術を望んでなかった。
丁寧に診察すると、首が痛くて動けないことが一番の問題であるように思えた。
心臓の所見は派手だったが、切実な課題は別なのかもしれない。
介護サービスも導入されていなかったため、準備期間としての入院を提案した。
鎮痛剤を使い患者の痛みが解決すると、心臓の病気があるとは思えないほど、ご飯をしっかり食べていた。
時々ムセて、しばしば熱が出ることもあった。
次の日には解熱していた。
おそろく誤嚥により一時的な炎症が起きたのだろう。
毎日何事もなかったかのようにご飯を全部食べたので、抗菌薬の投与は控えた。
血管の細くなった高齢者では何度も刺してしまうこともある。
穏やかに過ごす人に、針を向けるべきなのか?
そう疑問に思う。
患者の様子を慎重に観察して、本当に必要となるまで採血もしなかった。
採血だって苦痛を伴う医療行為である。
結果的に介護環境が整うまでの1ヶ月ほど、平穏な暮らしを送られた。
認知機能の落ちた患者は、何でここにいたのか分からないまま帰っていった。
循環器内科医の本分は、心臓の治療を提案することかもしれない。
手術や投薬で解決しない生活の問題に直面したら、「やれる事はやった、転院しましょう」と話す。
あるいは発熱のたびに採血やレントゲンを撮影し、食事を止めて抗菌薬を投与したかもしれない。
私のやり方は偶然良い結果を生んだだけかもしれないが、老年科医のやり方を真似たのは事実。
しかし売り上げが雀の涙、貴重なカテーテル症例を逃したこともまた、現実である。
良い医療には代償が必要なこともある。
選ぶことは簡単なのか
重大な決断を先延ばしにし、いざ切羽詰まった病状に直面すると答えを出す余裕がなくなる。
分岐点は“突然”訪れる。
延命治療の是非を問われたとき、自分では決めたくないという人も少なくない。
Tragic Choice(悲劇的な選択)という論文の序文が印象的だ。
『私は決めて貰いたかった。会ったこともない医師に…
私は間違った選択をしてしまう責任を負うことは出来ない。
彼女にとって正しい選択だと確信して選んだとしても、何かが上手くいかなかった時に、罪悪感を感じながら生きていくことなんて出来ない』
選択は重荷である。
日本人は特に、重要な判断を信頼できる誰かに委ねたいという傾向が強い。
延命治療をどうするか――
インフォームド・コンセント(IC)やアドバンス・ケア・プランニング(ACP)が機能しにくいのは、その責任の重さゆえかもしれない。
心理的負担を示す興味深い研究もある。
臓器提供の意思表示では、「希望するなら記入」するオプトイン方式より、「希望しないなら記入」するオプトアウト方式の方が、同意率が格段に高かった。
自分のことすら決めることを避けてしまう。
他者の人生に関われば、後悔が残る。
もっと良い方法があったのではないか、と。
Tragic Choiceでは心理学的な実験と考察から、医師が決定を下すと『避けられない運命』として受け入れやすい可能性も示した。
パターナリズムも常に悪では無い。
一方で、一本道のレールにストレスを感じることもある。
小さな選択が幸福に繋がり、選択権がないことは寿命すら縮める。
この矛盾を、どう乗り越えればいいのか。
答えの無い問いに、私が可能性を感じたのは質問の工夫。
些細な違いが、人間の心理に影響して、結果を大きく変えることは行動経済学のナッジ理論として知られる。
実験や理論を根拠にした小技はある。
しかし、スキルが全てなのだろうか。
良い医療を届けたいという想い
経験の浅い若い医師から終末期の話し方を聞かれたときに、内容の手解きをしたことがある。
彼らは熱心にメモを取り、シミュレートする。
そして患者や家族に相対した時、まるで原稿を読み上げるように話をする。
チェックリストを付けるかのごとく、必要事項を順に確認する。
内容や技術に拘ると、しばしば相手を置き去りにしてしまう。
ある循環器内科医は著書で心不全の治療を『アートする』と表現した。
アートとは言い得て妙である。
たしかに知識や技術が必要だが、それだけでは人の心を動かす作品にはならない。
制作者の強い想いが込められている。
終末期の物語も同じではないか?
エビデンスで外郭を組み立てて終わりではない。
用語の定義を照らし合わせる場でもない。
患者も家族も医者も看護師も他の医療スタッフも、皆が“良い医療”を目指したときに形になる。
そして治療の筋書きを描くのは医師である。
「こんなことやる必要があるのかな」
疑問を抱きながらの行動は、結果に繋がらない。
患者や家族は傍観者ではないが、残念ながら時間を掛けても他人事の人はいる。
医学教育では『正しい説明を繰り返す』と習うが、限界もある。
我々がシュレディンガー方程式を解けないことと同じ。
医療は難しすぎる。
お任せします、と丸投げする人がいたって不思議はない。
熟練のバリスタが一人ひとりの好みに合わせて一杯を淹れるように、“選択を提案”するという姿勢も、時に必要なこと。
ドイツの哲学者アルトゥール・ショーペンハウアーは『幸福は目立たず、苦痛の不在としてしか感じられない』と論じた。
最期を看取るとき、少なからず悲しみを生む。
しかし苦痛を和らげることは出来る。
それは麻薬による直接的な痛みの軽減だけではない。
外来で1分だけでも良いから話し合い、決断の苦しみを減らすよう配慮する。
そのために工夫できる場面があるはず。
医師は技術や理論を磨くことには慣れている。
だが、それをどんな想いで使うか。
――どう死ぬと不幸が少ないか。
その問いに向き合うなかで、私もまた、学び続けている。
目指したい終末期医療の在り方は、最期を迎える人達に「良い選択をした」と納得してもらうことである。
主要な参考文献
Boult C, Boult LB, Morishita L, Dowd B, Kane RL, Urdangarin CF. A randomized clinical trial of outpatient geriatric evaluation and management. J Am Geriatr Soc. 2001 Apr;49(4):351-9.
Studdert DM, Mello MM, Sage WM, DesRoches CM, Peugh J, Zapert K, Brennan TA. Defensive medicine among high-risk specialist physicians in a volatile malpractice environment. JAMA. 2005 Jun 1;293(21):2609-17.
Givens JL, Jones RN, Shaffer ML, Kiely DK, Mitchell SL. Survival and comfort after treatment of pneumonia in advanced dementia. Arch Intern Med. 2010 Jul 12;170(13):1102-7. doi: 10.1001/archinternmed.2010.181. Erratum in: Arch Intern Med. 2011 Feb 14;171(3):217.
Simona Botti, Kristina Orfali, Sheena S. Iyengar, Tragic Choices: Autonomy and Emotional Responses to Medical Decisions, Journal of Consumer Research, Volume 36, Issue 3, October 2009, Pages 337–352
Langer EJ, Rodin J. The effects of choice and enhanced personal responsibility for the aged: a field experiment in an institutional setting. J Pers Soc Psychol. 1976 Aug;34(2):191-8.
エピソードは個人が特定されないよう手を加えいます。
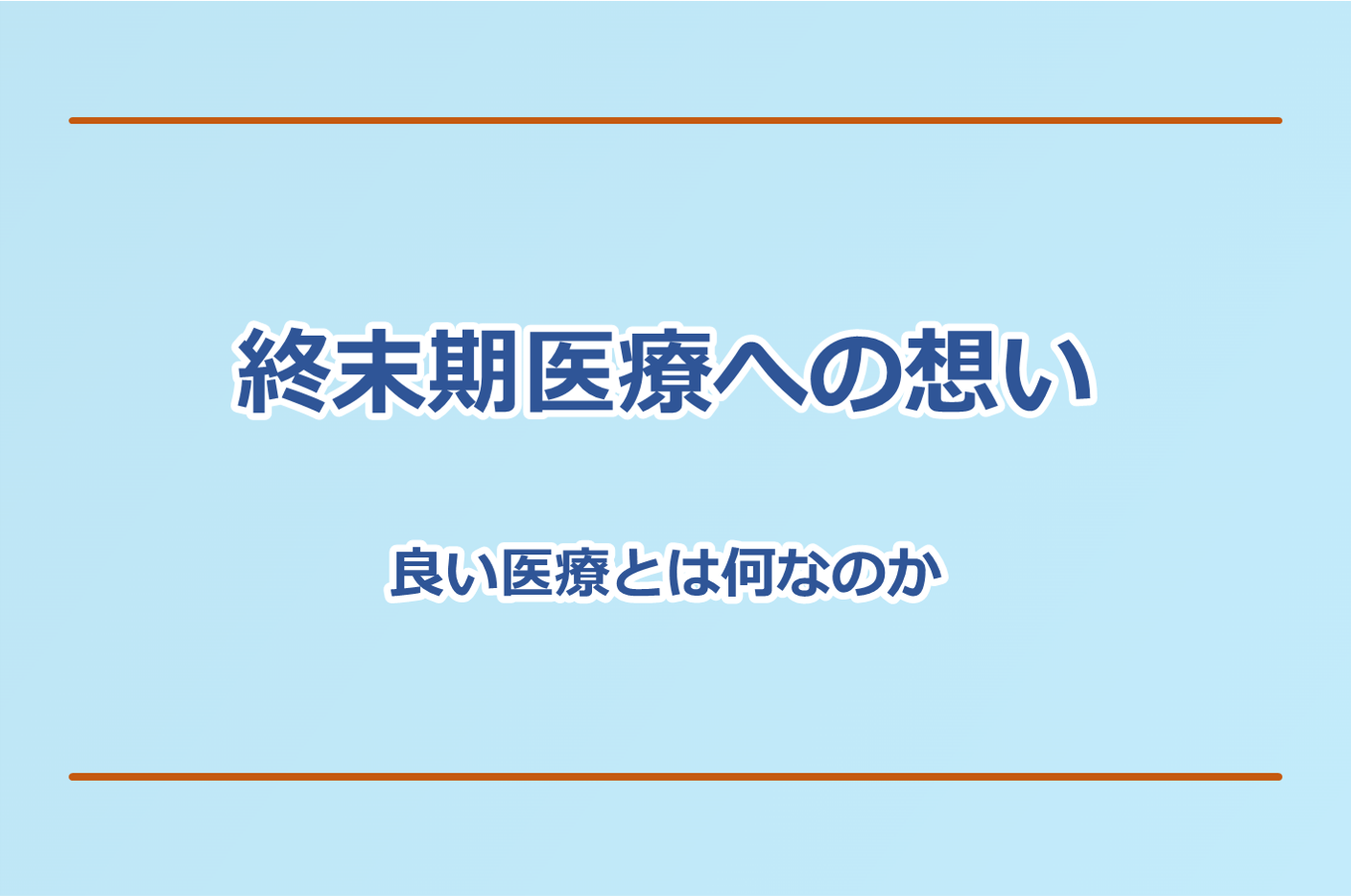
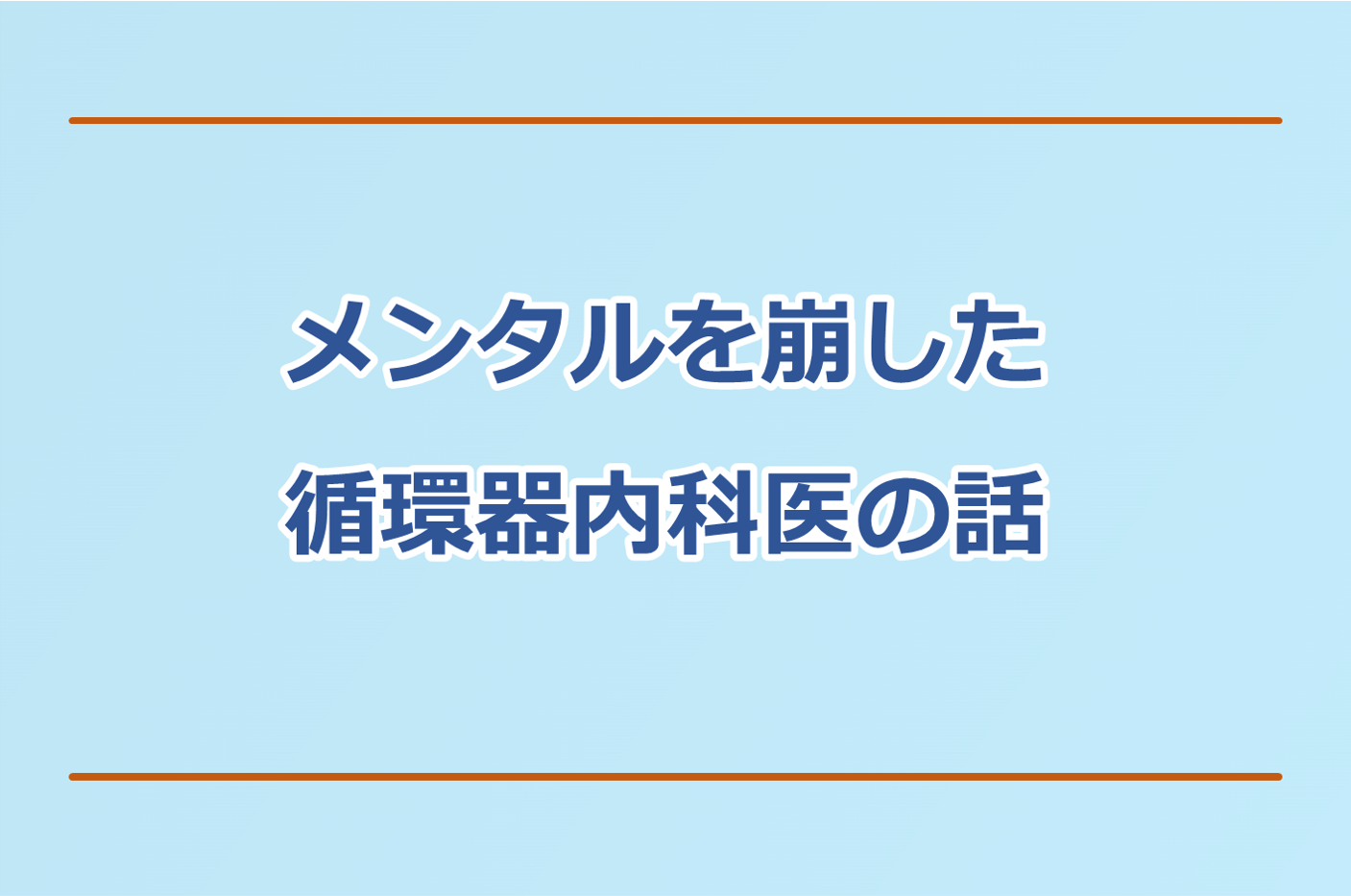
コメント