ストロングスタチンは診療の中でしばしば耳にする単語ですが、実は分かったような分からないような言葉だと思います。
少し掘り下げてみようと思います。
High-intensity statinという概念の輸入
もともとhigh-intensity statinは、米国のACC/AHAガイドラインにおいて、「LDL-コレステロールを50%以上低下させる用量のスタチン」として定義されています。具体的には
・アトルバスタチン40–80 mg
・ロスバスタチン20–40 mg
が該当します。
これらは心血管イベント予防におけるエビデンスに基づく用量ですが、日本では高用量のスタチンは副作用リスクや保険制度の制約から使いにくいのが実情です。
日本での高用量スタチン使用の制限
日本では、たとえばロスバスタチンは最大20mgまでしか保険適応がありません。
アトルバスタチンも20mgが上限です(家族性高コレステロール血症は40mg)。
欧米のhigh-intensity相当の用量を使おうとすると、量によっては保険適応外使用になってしまいます。
また海外と日本では体格差や人種差がありまったく同じ用量が望ましいとも限りません。
実際にエフィエント(抗血小板薬)やイグザレルト(抗凝固薬)は、日本では海外よりも少ない用量で承認されています。
「ストロングスタチン」という国内独自の用語の登場
保険適応の制約などの背景から、日本では「high-intensity statin」という概念をそのまま適応できず、「比較的LDL-C低下作用が強いスタチン群」を「ストロングスタチン」と呼ぶようになりました。
この分類には以下の薬剤が含まれます:
・アトルバスタチン
・ロスバスタチン
・ピタバスタチン
これらは中等度の用量でも30~50%程度のLDL-C低下作用を持つことから、プラバスタチンやシンバスタチンなどと区別して「ストロング」と呼称されるようになったのです。
呼称のすり替えの意図
したがって、「high-intensity」というエビデンスベースの用語を使えない代わりに、「ストロング」というやや曖昧で保険制度に適合した表現が普及したのはと思います。
「ストロングスタチン」という用語が日本の医学文献で初めて登場した正確な時期を特定するのは困難ですが、2010年くらいから出現したのではないかと思います。
例えば、2011年に報告されたPATROL試験では、これら3剤の有効性と安全性が比較され、いずれも「strong statin」として位置づけられ、論文内では近年日本でそう呼ばれていると記載があります。
「ストロングスタチン」という用語は、日本の医療制度や保険適用の制約の中で、欧米の「high-intensity statin」という概念を適応させるために生まれた、日本独自の表現と考えられます。
その背景には、心血管疾患予防のために強力なLDLコレステロール低下が求められる一方で、高用量スタチンの使用が制限されているという事情が関与していそうです。
参考
Saku K, Zhang B, Noda K; PATROL Trial Investigators. Randomized head-to-head comparison of pitavastatin, atorvastatin, and rosuvastatin for safety and efficacy (quantity and quality of LDL): the PATROL trial. Circ J. 2011;75(6):1493-505. doi: 10.1253/circj.cj-10-1281. Epub 2011 Apr 15. PMID:21498906
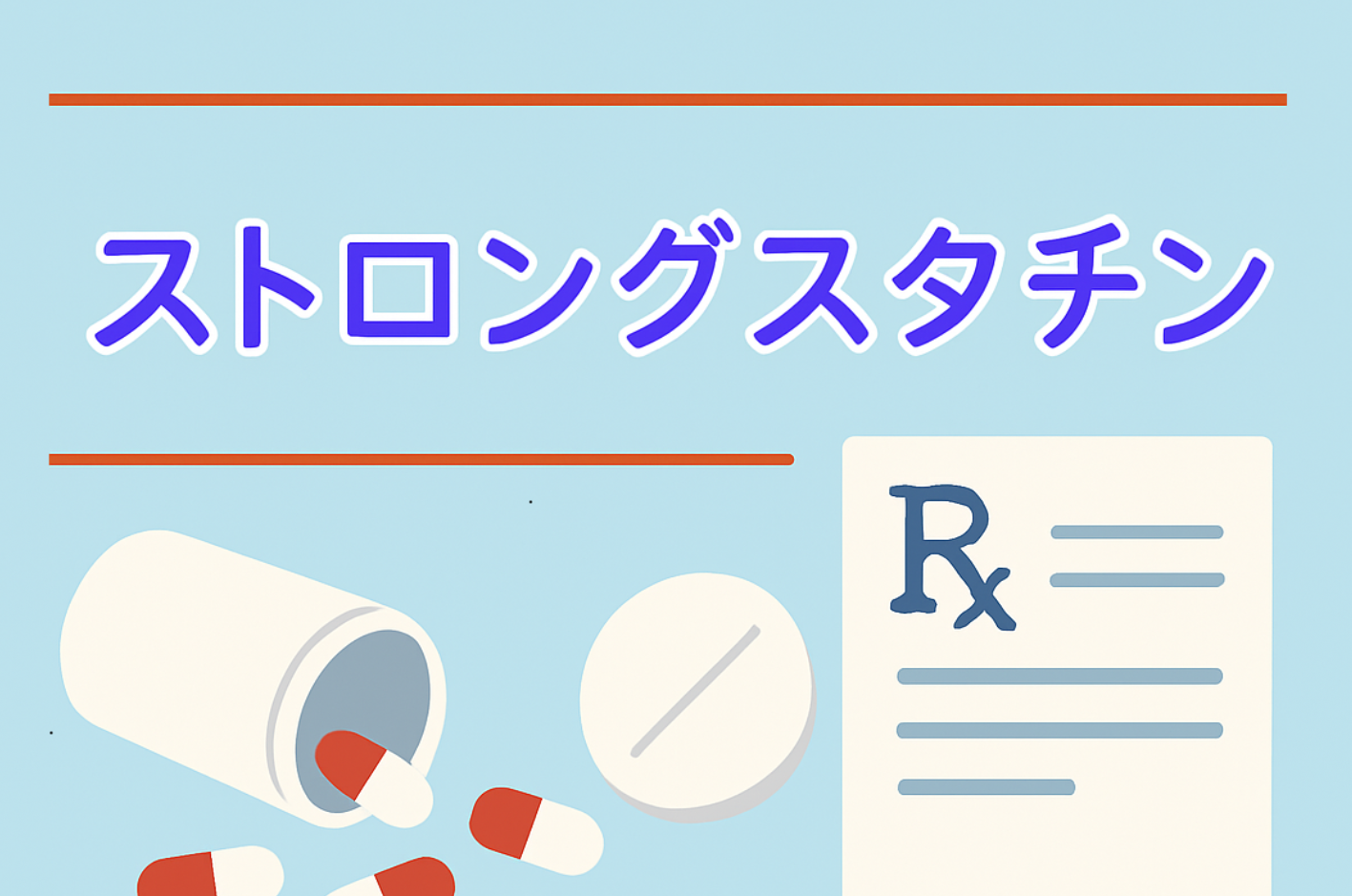
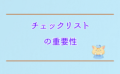
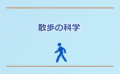
コメント